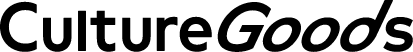企業理念に共感する社員はたった2割?価値観をホントに浸透させる方法
会社づくりの基本として、「パーパス」「ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)」の設定は当たり前となっています。しかしそれが本当の意味で組織の形成と発展に役立っているか、自問自答して悩む経営者も少なくないのではないでしょうか。この記事では、会社が設定したパーパスや価値観を、真の意味で組織に浸透させるためのヒントを提供します。
会社のパーパスやMVVはなぜ大事か?
「ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)」というまとまった言葉で表現されたのは、「経営学の神様」と呼ばれる学者であるピーター・ドラッカー氏が、2000年代初頭に発表した「ネクスト・ソサエティ」で重要性を提唱したことが由来と言われています。
テクノロジーの進化により急成長を遂げるスタートアップが出てきたことにより、多くの創業者が事業拡大を成功と位置づけ、組織を大きくしたり資金調達をするなかで、自社が一体どういう事業なのかを伝える根幹となるのが「MVV」です。既にたくさんの企業が存在するなかで自社がなぜ新しい事業を起こすのか、そして先を完璧に見通すことの難しいVUCAの時代にも確固たるものとして判断基準となる指針を持つことが、会社の死活問題に関わってきます。
事業が成長すれば、様々な人が関与することになり、考え方も多様となってきます。よりよいサービスやモノを提供し、あらゆる側面からのリスクを低減させるには多様な考え方によっていろんな視点からのチェックが役立ちますが、進みたい方向についても異なる考え方で運営されてしまうと、衝突や乖離が生まれ事業を続けることができません。そのために、会社の果たすべき使命「ミッション」を掲げ、実現したい「ビジョン」を定義した上で、組織や社員の行動としてどんな価値観で仕事をしてほしいかの拠り所となる「バリュー」を定めることが重要です。
さらに最近では「パーパス」を新しく定める会社が増えています。日本でいう経団連のアメリカ版である「ビジネスラウンドテーブル」の2019年の会合で、企業の存在目的(=パーパス)はこうであるべきだ、という宣言が発表され、同年に世界最大の資産運用会社であるブラックロックのCEOの書簡でパーパスの重要性を述べられたことから注目を浴びました。
長年の課題ではありますが、SNS等の発達によりますます負の部分が訴求されるようになった環境問題や人権などの社会問題は、そもそも企業の行動により悪化した側面もあります。しかし、もともとどの会社も世の中に役立つモノやサービスを提供しようと創業しているはずです。そこで本来目指していた会社のあり方を見直し、会社が存在する意義を再定義しようという動きが高まってきているのです。特に新型コロナのパンデミックは働き方や人生について深く見直す機会となり、ますます「何のために」が大事になってきていると言えるでしょう。
パーパスや価値観浸透のステップ
せっかく定めた企業の考え方も、組織に浸透しなければ思うように動けません。理念の浸透には大きく3段階の濃度があります。

認識する
企業のパーパスやMVV、価値観などを採用や入社のタイミングで広く周知すれば、従業員は何度か目にする機会があるでしょう。特に採用では、応募者自らが企業研究するなかで、会社のパーパスやミッションが気にいって入社を決めることもあります。既に自分の行動や特徴に合致し、深い共感ができている場合もありますが、スキルや経験で評価されて入社を決めた場合には、言葉を目にした程度で「会社のミッションは?」と聞いても空では出てこないケースもあるかもしれません。まずは言葉を覚えてもらうことから始まります。
納得・共感する
従業員がある会社に所属して働いているということは、会社の生み出すモノやサービス、働く仲間の価値感、方向性など何かしらの形に共感しているからこそです。もともと会社の組織と従業員の心を結び付けていたものが、パーパスやMVVなどの明文化されたものによって、従業員がより納得感をもって組織で活動することができます。言葉の理解が進むと、自分の言葉で表現できるようにもなるでしょう。
行動に反映する
企業の理念を把握し、共感したその先に行動への反映があります。そもそも組織全体をある方向に動かすために設定しているので、組織の一員である従業員が行動に反映することが出来なければ、パーパスやMVVを設定する意味がありません。企業によっては「クレド」という形で日常生活での具体的な行動指針を明文化している場合もありますが、日々従業員が行う判断に、「企業の存在意義が○○だから、○○するのが正しい」「会社は○○に価値を置いているから、それに沿った○○を選ぶ」といった形で取り入れられるのが理想です。
企業理念やカルチャーを浸透させるには頻度が大事
何事も浸透させるには時間のかかるものです。もちろんもともと深く共感している社員やインパクトのある文言なら内容の理解までは早く進むかもしれませんが、行動にまで結びつけるのは簡単なことではありません。
博報堂が実施した「ブランドパーパスに関する生活者調査」によると、企業に勤めている人のうち、理念を知っている人は8割であるのに対し、共感している人はたったの2割強に留まります。

本来企業の何かしらに繋がりを感じて所属しているはずの従業員に、明文化された理念の理解と共感、そしてそれに基づく行動をしてもらい、企業が目指したいカルチャーを育んでいくには、繰り返しの説明と形を変えた表現が重要になります。
企業理念やカルチャーを浸透させる施策としては様々なものがあり、頻度の多さと実施難易度の高さにより下図の4象限にまとめられます。
従業員への理念やカルチャー浸透のための、接点頻度が高く難易度の低い関わり方としては直接上司が部下に話をする1on1や食事会が挙げられますが、新型コロナの影響で対面がなかなか難しくなりました。今後規制が緩和されることで対面型の施策も再開されることになりますが、コロナを機にハイブリッドやフルリモートに転換した組織もあり、依然として気軽な実施が難しい場合もあります。
カルチャーグッズなら、明文化された企業理念などを普段使うグッズに印字することで、目にする機会が必然的に増えます。またその言葉が意味することをモノで表現することにより、理解の促進にもつながります。

まとめ
CultureGoodsなら理念浸透に役立つグッズをワンストップで制作できます。
グッズに入れる言葉の選定から、加工、渡すときの演出までグッズプランナーがアドバイス、企業理念の浸透に向けてしっかり伴走します。
理念浸透に最適なグッズのセレクションはこちらをご覧ください。
参考文献:
博報堂 「ブランドパーパスに関する生活者調査」 https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/87994/
Ranking


カルチャーグッズで
企業の「らしさ」を作る
カルチャーグッズで企業の
「らしさ」を作る
私たちカルチャーグッズが大切にしているのは、
あなたがグッズ作りに込める「想い」。
だからこそ、商品の質にこだわり、一つ一つの案件に必ず担当者がついて、
一緒に作り上げます。
オーガニックコットンを使用したTシャツなど高品質なグッズに、
職人さんが丁寧に加工します。
少し根は張るけど、あなたの企業「らしさ」を実現したオリジナルグッズを
お客様や社内メンバーに贈りませんか。
商品ラインナップや進め方も一から説明します。まずは、ご相談ください。
私たちカルチャーグッズが大切にしているの
は、あなたがグッズ作りに込める「想い」。
だからこそ、商品の質にこだわり、
一つ一つの案件に必ず担当者がついて、
一緒に作り上げます。
オーガニックコットンを使用したTシャツな
ど高品質なグッズに、職人さんが丁寧に
加工します。
少し根は張るけど、あなたの企業「らしさ」
を実現したオリジナルグッズをお客様や社内
メンバーに贈りませんか。
商品ラインナップや進め方も一から
説明します。
まずは、ご相談ください。